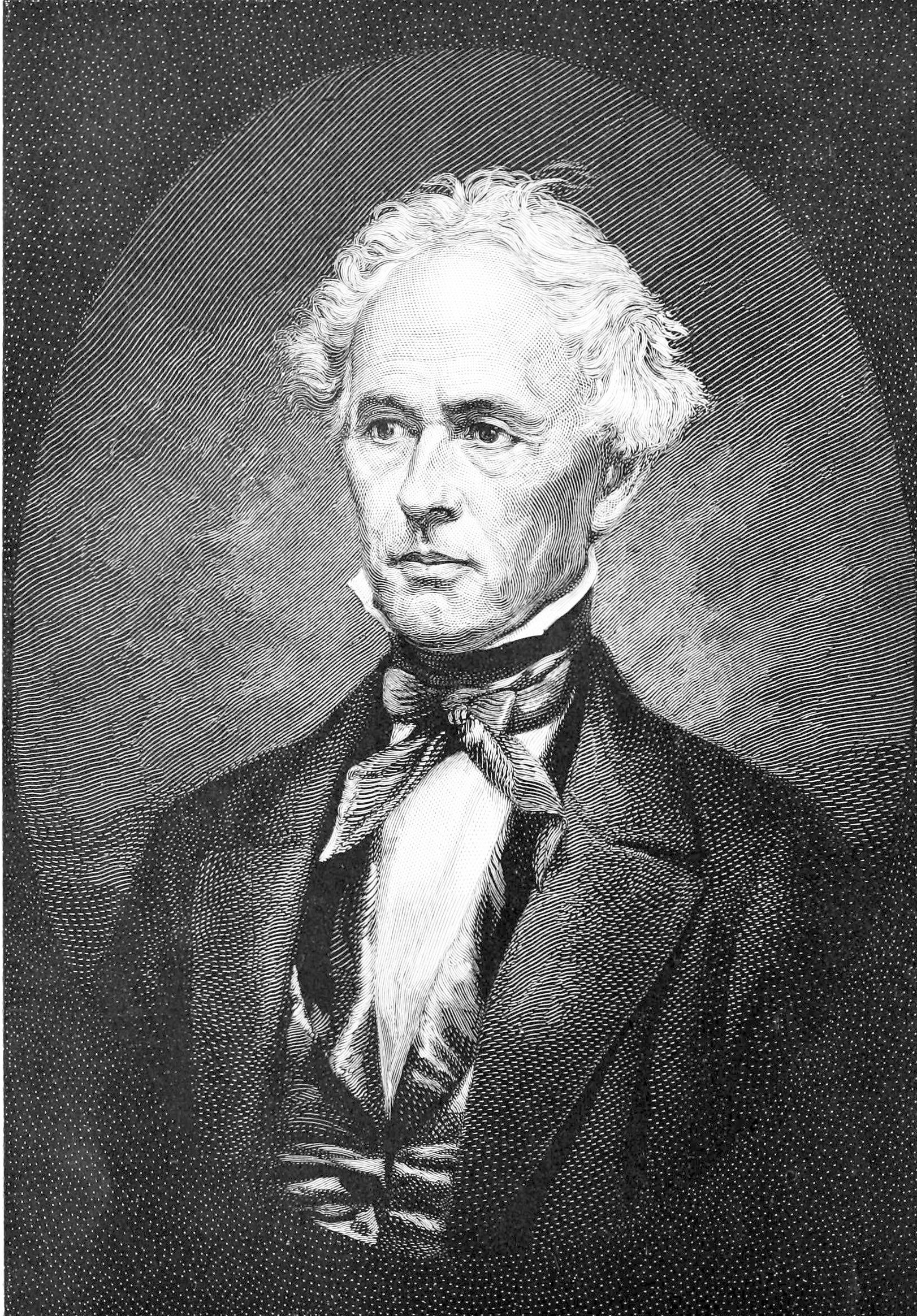学会が大規模な気象観測網を構築するようになったことは、「学会と気象観測」のところで述べた。イギリスの王立協会で行っていた気象観測網の結果を記録するということを最初に唱えたのは王立協会のウィルキンス(John Wilkins)だが[1]、本の3-3-3「イギリスの王立協会とフック」で述べたように、ロバート・フック(Robert Hooke)が1663年に気象観測網での具体的な観測様式や計画を「気象誌の作成方法(A method for making the history of the weather)」として作成した。フックとは、ばねの弾性の法則である「フックの法則」として有名なあのフックのことである。本の4-3「温度計の発達とその目盛りの変遷」で述べたように、フックは温度計の測定基準(calibrating thermometers to obtain consistent values)を確立しようともした。 そういう意味では、フックは組織的な気象観測網の意義を理解して確立しようとした一人と言える。
 |
| 「気象誌の作成方法」に記載された様式。Sprat, T (1702) The history of the Royal Society of London, for the iproving of natural knwoledge, fourth edition, London |
本の4「気象測定器などの発展」で触れたように、フックはほとんどあらゆる気象測定器の改良にも尽力している。これらも考慮すると、フックによる気象観測の発展への貢献には、歴史的に欠くべからざるものがある。
ところが、根本順吉氏が指摘しておられるように、気象学史の本にフックの業績について詳しく触れたものは少ない。この理由としてやはり同氏による指摘のように、気象学は応用物理学の一部門としてしか見られず、気象学が独自に発展した面が軽視されている[2]からなのかもしれない。
(次は「ケッペンについて1」)
参照文献
[1]根本順吉 (1964) 気象学史物語XXV気象観測事始(1), 気象, No.8, 1
[2]根本順吉 (1964) 気象学史物語XXVI気象観測事始(2), 気象, No.8, 2
[最上部の「気象学と気象予報の発達史」クリックすると最新のブログに跳びます]