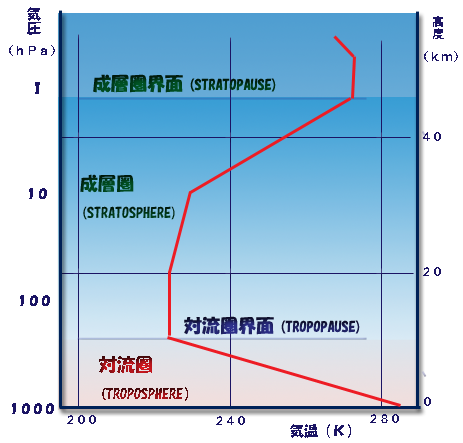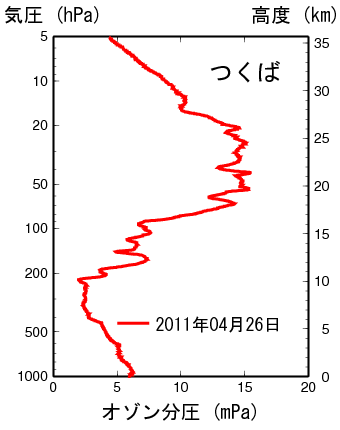ウィリアム・ダインス(William Henry Dines)
ダインスの家系
| 父のジョージ・ダインス |
しかし、建築物は気象の影響を受ける。信頼される建築物を作るためには、風や雨、湿度、結露などの建築物などへの影響を調べる必要があってか、父のジョージ・ダインスは気象の測定に強い関心があった。ジョージは、1864年にイギリスの王立気象学会のメンバーに選ばれており、「ロンドン地区の雨量(Rainfall of the London District) (1813-1872)」を出版した(Pike, 1987)
父ジョージ・ダインズの建築業は成功しており、ロンドンでいくつかの建物を所有していたため、これらからの安定した収入があった。これによって、父と息子のウィリアム・ダインスは、気象学に対する研究を熱心なアマチュアとして追い続けることができた(Pikes, 2005)。しかも、ウィリアムの子のうち、兄のLewen Henry George Dinesはケウ気象台(Kew Observatory)の技師となり、弟のJohn Somers Dinesはロンドン気象局の技師となった。大変珍しいことに、3代続いた気象学者の家系となった。
若い頃の経歴
ダインスは少年時代にはロンドン南西にあるウッドコート学校に学び、そこで数学に傑出した才能を示した。彼は有名なトリニティ・カレッジに進んだが、そこで彼独自のやり方を認めない数学教師と衝突したため、父は16才だった彼を自宅に戻した(Pikes, 2005)。1873年から彼は南西鉄道会社の工場(The Nine Elm Works of the Southwestern Raiway)に見習エ(apprenticeship)として入社した。彼はそこで優れた製図技術を身につけ、後に彼がさまざまな革新的な気象測定器の設計図を作成する際に、それが大きく役に立つこととなった。また、彼はそこで風に興味を持ち、機関車のテスト走行時に彼が実際に乗って感じた風の速さや圧力の感覚は、後のテイ鉄道橋の大惨事後の風速の議論にも役に立った(Pikes, 2005)。
1877年にダインスは4年間勤めた鉄道技手を辞めて、ケンブリッジのコーパス・クリスティ大学(Corpus Christi College, Cambridge)の数学科に入学し、1881年に卒業した。彼はモーソン奨学金を受けるなど数学に才能を示したが、彼が在学中の1879年に起こったテイ鉄道橋の大惨事は、彼を気象学の道に進ませることとなった。
(つづく)
参照文献
Pike-1987- Master builder turned meteorologist; George Dines, 1872-1887, Weather, 42, 88-90Pike-2005-William Henry Dines (1855-1927),Weather, 60, 308-315.