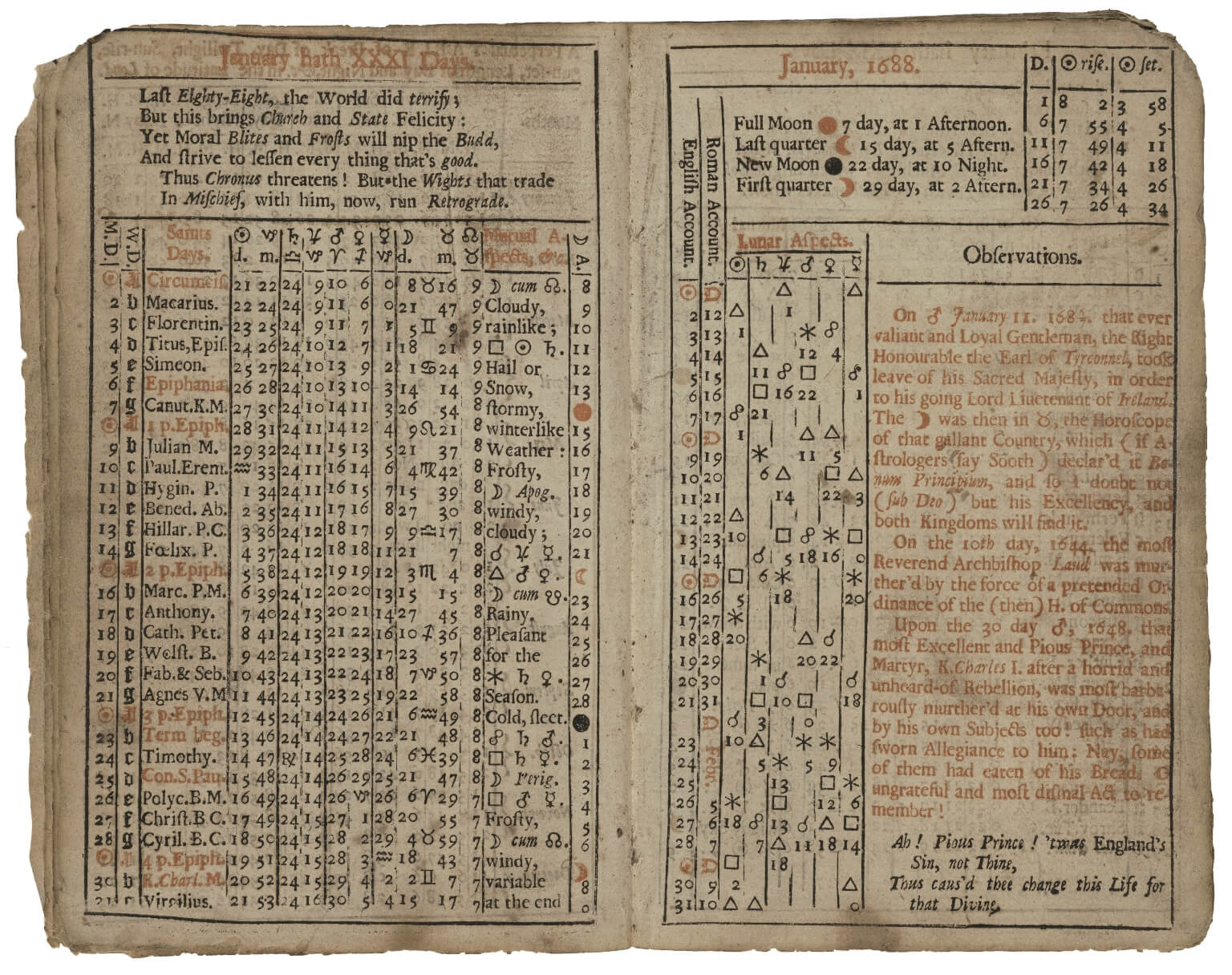(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です )
天気図を見て主観に基づいて行う気象予測は科学とは言えず、アメリカの気象学者アッベなどは物理法則を用いた科学的な気象予測を唱えたが、当時の観測技術や未成熟な気象学では困難だった。
20世紀に入ると、ノルウェーの物理学者ヴィルヘルム・ビヤクネスは気象を物理法則に基づいて定式化すれば、「観測データの整備によって客観的にかつ決定論的に気象予測ができる」という考え方を提唱した。彼は気象学者に転向して実際に気象予測のための物理方程式(プリミティブ方程式)を定式化し、高層気象観測データを用いた予測手法を構築しようとした。これは決定論的な手法だった。気象予測のための方程式は解析的には解けないため、彼は所長となったライプチッヒ地球物理学研究所において、解析天気図を組み合わせていく視覚的な手法を検討した[9-1ヴィルヘルム・ビヤクネスによる気象学の改革](このブログの「大気力学でのソレノイド」も参照)。
一方で、イギリスの気象学者リチャードソンは、気象予測の物理方程式(プリミティブ方程式)を高層気象観測データと差分法を用いて、直接的に数値計算することを考えついた。そのためには膨大な計算が必要なるが、彼は第一次世界大戦中に志願して戦場で救急車を運転する役目を果たしながら、その試行的な予測計算を実践した。しかし、当時は気象を引き起こしている波と数学的な差分法の特性が十分理解されておらず、この野心的な挑戦は非現実的な予測結果となって失敗に終わった。しかし、この手法は原理的には現在の数値予報の考え方を先取りした革新的なものだった[9-3リチャードソンによる数値計算の試み]。
一方で、予測技術の行き詰まりの打開のために、高層の気象観測による新たな発見に期待が寄せられた。また第一次世界大戦において、高層を飛ぶ長射程砲弾のための軌道修正と発達し始めた航空機の運行に対して、地上天気図が役に立たないことがわかり、それらが高層気象観測の充実を加速した[9-1-7第一次世界大戦の気象学と収束線]。
さらに戦争中の食糧危機に対して、気象情報を使って農業、漁業の増産を図ろうとしたノルウェーでは、ヴィルヘルム・ビヤクネスがドイツから帰国して、高密度の気象観測網を展開した。このこれまでにない密な観測網から、寒帯前線論や気団という気象予測のための新しい概念が生まれた[9-2ベルゲン学派の気象学]。これらは決定論的な手法ではなかったが、それまで予測できなかった天候の急変などをある程度予測できるようになり、また高層雲の変化から悪天候の接近を予測するという新たな手法にも結びついた。
1930年頃からは、ラジオゾンデの発明により高層気象観測はゾンデ回収の必要がなくなり、観測と同時に結果がわかるようになった。これによって高層気象観測の密度と頻度が向上した[9-4-3世界でのラジオゾンデ観測の発達]。この観測による高層大気の広域的な把握は、ロスビーによる高層の長波の発見につながった。またこの長波と地上の低気圧や前線との関係もわかってきた。そのため、地上の気象予測のために長波の動きを予測する手法が開発された[9-5高層の波と気象予測]。さらにアメリカのチャーニーにより大気の立体構造から低気圧が発達する原因に関する理論(傾圧不安定理論)が生まれ、高層の地球規模の大気循環と地上の天気が結びつけられた。これらにより気象予測は初めて科学に立脚するものとなっていった[10-3-2傾圧不安定理論の確立]。
 |
| ラジオゾンデ |

.jpg)