彼は出島滞在中に江戸に行くことになり、その途中で日本の象徴である富士山の高さを計測することを計画した。しかし、外国人の行動に対する幕府の監視は厳しく、1828年に本人の代わりに蘭学者で弟子の二宮敬作(1804-1862)が実際に富士山に登って高度を計測した。二宮敬作はおそらく気圧計と温度計を使ったと思われる。既に当時は高度を現地気圧と気温から推定できることがわかっていた[4-8測候高式の発見]。彼は富士山の高度を3794.5 mと算出したらしい。これは実際の高度との差はわずか約20 mという高い精度での測定だった。しかしこの観測は秘密裏に行われ、日本では正式な記録として残らなかった [1]。
 |
| 晩年のシーボルト (Unknown artist, "E. Chargouey", Naturalis Biodiversity Center - Siebold Collection - Philipp Franz von Siebold - Portrait, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons) |

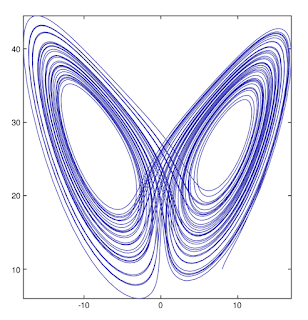


.jpg)