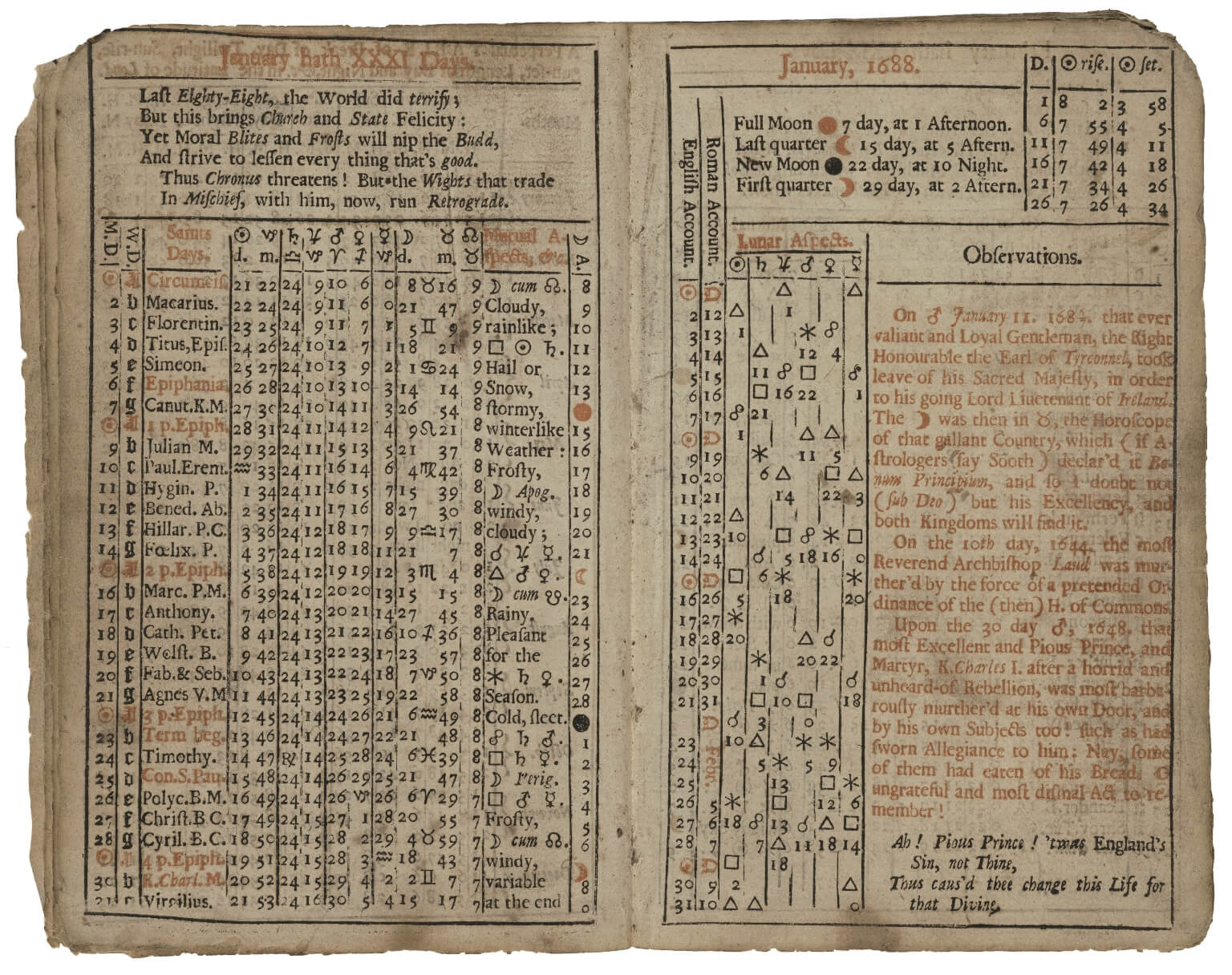(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です )
18世紀後半から国家という概念が明確になってくると、産業、経済、健康、植民地経営のための地理情報という観点から、気象・気候が重要視されるようになってきた。気象データの蓄積だけでなく、気象観測網を各地に展開しての気候の把握が重要となった(このブログの気候学の歴史(1)
~(10)参照)。観測結果を用いた気候統計が行われて、各地の地誌学的な気候情報が整備された[5-1気候学の発展]。過去の観測値を用いた総観天気図も作られたが、それはまだ試験的なものだった。
 |
| イギリスの気象学者アーバークロンビーによる7種の気圧分布の分類。 彼の著書「Weather (1887)」より。 |
また19世紀末から気球を用いた高層気象観測が行われるようになり、ゴム気球の発明(このブログのリヒャルト・アスマン(その2)参照)や成層圏の発見(このブログの高層気象観測の始まりと成層圏の発見(1)~(12)参照)などが起こった。しかし高層気象観測は、気球による大気の持ち上げや日射の測定器への影響の問題に加えて測定記録の回収が必要であったため、20世紀に入ってもまだ定常的な広域観測は困難だった[8-4高層大気の気象観測]。
.jpg)