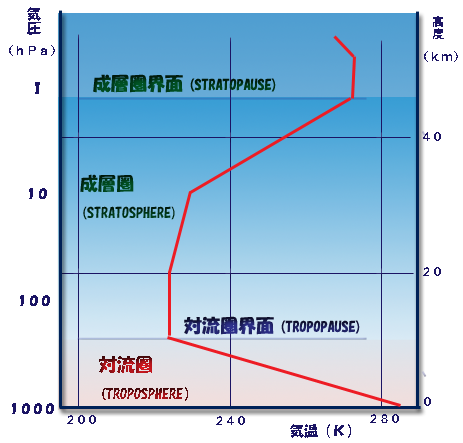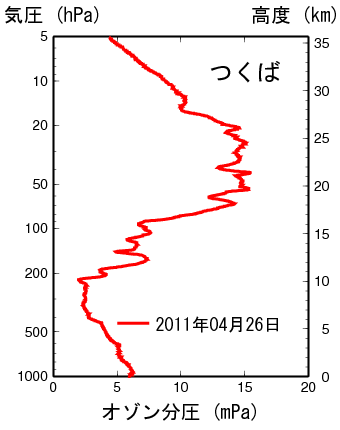ダインスは、風杯型風速計ではガストのような瞬間的な風速を過小評価する一方で、平均風速を過大評価していると感じていた(Pike, 1989)。これが本の4-4「風力計・風速計」で述べるように、彼が圧力管風速計(pressure-tube anemometer)を開発する動機となった。
 |
| ロビンソン式4杯型風速計 |
風速計の調査
また父のジョージ・ダインズもこのテイ鉄道橋の事故によって、建築技術者として将来の構造物が耐風性についてどの程度の許容があるのかを正確に知る必要があると感じていた。ジョージは1887年に、ハーシャム(Hersham)にあった自宅の庭で、息子のウィリアム・ダインスと風速計の過大評価に関する実験を行い始めた。まもなく父ジョージは亡くなったが、この実験は息子のウィリアムに引き継がれた。その結果、ロビンソン式風杯型風速計の係数は3よりは2.15に近いことがわかった(Pike, 2005)。これは、これまでの記録が実際の風速と圧力をほぼ3分の1ほど過大に評価している(つまりこれに耐え得た強度基準は過小評価になる)ことを意味した。
(つづく)
参照文献
- Pike-1989-One hundred years of the Dines pressure-tube anemometer, The Meteoroloical Magazine, 118,1407, 209-214.
- Pike-2005-William Henry Dines (1855-1927), Weather, 60, 308-315.